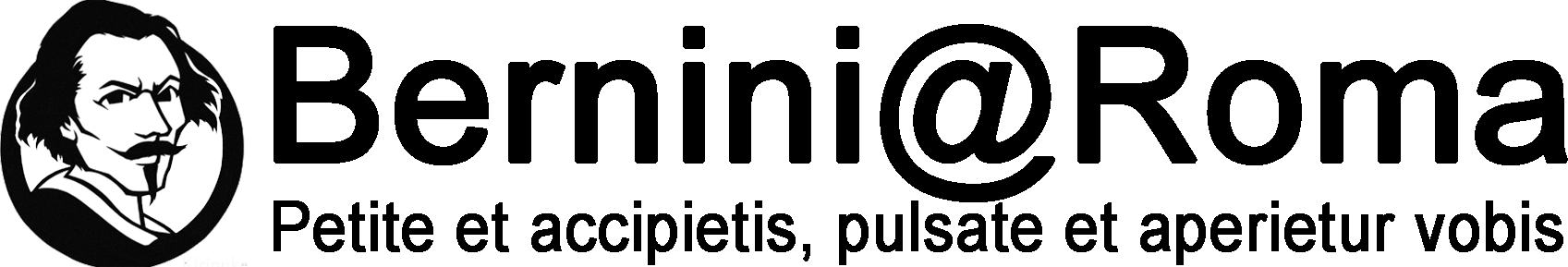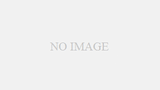作者の名はジャン・ロレンツォ・ベルニーニ。わずか二十五歳でこの天蓋の製作を任され、以後法王の芸術家としてサン・ピエトロ大聖堂の内装から、284本の柱からなる回廊をもった聖堂前の広場の製作まで指捧をとったのが彼である。また有名なトレビの泉も彼の作品だ。古代ローマの遺跡群とともに、ローマの街に特異な表情を与えている、豪華さと人を驚かすエンターテインメント性がきわだつバロック芸術の生みの親だ。
さて、例の出産シーンにかんしての伝説や仮定はいくつかある。ひとつめの伝説は、当時妊娠していた法王ウルバーノ八世の姪が寄進したというもの。無事出産を終えることができたら、ベルニーニがその吉事を台座に刻むことになっていたというものだ。しかし、出産の最後の瞬間までつづくあの苦しそうな表情は、吉事の記念としてどうかとも思うし、なにより性器をリアルに措かれることを名家の姫が承知したとは思えない。
宗教的な意味合いからの仮説もある。新約聖書のジョバンニ(ヨハネ) の福音書にある、「人は新たに生まれなければ、神の国を見ることばできない」 や、「女は子どもを産むとき苦しむものだ。自分の時がきたからである。しかし子どもが生まれると、ひとりの人間が世に出た喜びのために、もはやその苦痛を思い出さない」などのフレーズからインスピレーションを受けたとするものだ。宗教的な再生も生き物としての誕生も、どちらも楽なものではなく苦痛を伴うものと解釈すれば、あの彼女の苦しげな表情は説明がつくかもしれない。
ほかに、苦節9年間をかけた天蓋の製作期間を妊娠期間になぞらえ、天蓋完成後に記念としてこの浮き彫りを刻んだとする説もある。しかし、万が一その作業段階で台座にヒビでも入ったときには取り返しがつかない。めったにだれも気づかないであろうヒビが、完成後のある胸像に入っているのを発見したベルニーニは、丸ごとその胸像をつくりなおしたという。11メートルのブロンズの柱をまた立て直さなければならなくなる、そんなリスクをベルニーニが犯したろうか。
さて、数ある伝説のなかでもっとも有名なのがつぎのものである。 若きベルニーニは、時の法王ウルバーノ八世の姪と恋仲になり、ふたりは結婚を考えるまでにいたった。しかしいくら天才的とはいってもしょせん生まれの低いベルニーニと、ローマでもっとも権力をもっていた家族出身の姪っことの結婚を、法王はけっして許そうとはしなかった。しかし法王の反対にもかかわらず、彼女はついに身ごもり、ベルニーニの子どもを産み落とす。しかしこのことがさらに法王のいら立ちをあおることとなってしまい、ふたりは結局、法王によって引き裂かれるのである。ベルニーニはこの若き日の苦い経験と報われなかった愛を、天蓋の台座の石のなかに永遠に封じこめたという。
いかにも人びとが好みそうなメロドラマである。しかし、もしもこれが事実であれば、今も昔も大のうわさ好きのローマっ子たちが黙っていたわけがない。しかしそういった資料はいまのところみつかっていないのだ。いっぽうベルニーニの後援者であった法王ウルバーノ八世とベルニーニの関係については、時のローマっ子たちはこううわさしていた。
「法王は起きている間ベルニーニを片時もはなさず、やれ新しい教会だ、やれ新しい式典の準備だと設計図をのぞきこんでいる。ベルニーニがシーツをかけてやらぬかぎり寝床にもつかぬ」
法王という絶対的な権力者を後援者としてもつことで、この法王の在位した二十年間というもの、ベルニーニは各地からローマに集まってきた芸術家たちの実質的独裁者でありつづけた。彫刻や絵画という一点ものの作品をつくる芸術家というより、サン・ピエトロ大聖堂の天蓋や広場など、とてつもなく規模の大きな芸術的建設事業の監督となったベルニーニは、そこで必要とされる労働力としての芸術家の選択権をもっていた。
法王の発注した仕事につくことは、芸術家にとっては人生のチャンスにほかならない。給料が安かろうが自分の名前が表に出まいが、いつか法王にお目通りがかなうはず、と願って働きつづけた無名の芸術家が何人もいたことであろう。しかしベルニーニは法王の寵愛をほかのどの芸術家にも分け与える気などさらさらなかったようだ。「彼が金を手にするのに腹は立たない。しかしわたしの労苦をおのれのものとして誇っていることが口惜しい」。ベルニーニとともにバロック芸術の旗手といわれたボッロミーニの言葉である。うわさ好きのローマっ子の目を盗み、これほどの 「おいしい立場」と引き換えにしてもよいと思えるドラマティックな恋を、ベルニーニがしていたと考えるには、やはり多少の無理がある。
ではこの伝説は事実無根のまったくの想像なのか、といえばそうではない。法王が「待った」をかけた若き日のベルニーニの恋は、たしかにあったのである。
1628年、天蓋のブロンズの柱が大理石の台座にようやっと立てられた翌年、ベルニーニはミケランジェロの丸天井を支える四つの巨大な柱の装飾にかかわる新プロジェクトを始動させた。そのプロジェクトのチームにマッテーオ・ボヌチェッリ(もしくはボナレッリ)というトスカーナ地方出身の三十代の男が加わった。彼もひとかどの芸術家ではあったのだが、なによりも彼の恵まれていた点はその妻であったという。生気に満ちた強さと甘さをかねそなえた顔、頭の上で束ねられたカラスの羽のように真っ黒な髪、胸元からこぼれるはじけんばかりの胸。その名をコスタンツァといった。
ベルニーニとこの人妻の問にいつ特別な感情が生まれたのかを限定するのはむずかしい。夫人が、夫の彫った天使の像が見たい、あっちの天使の像の試作品が見たい、と言いながら、夫とベルニーニの働くサン・ピエトロ大聖堂の工事現場に足しげく通いはじめたころは、ふたりの関係はまだただのうわさでしかなかった。しかし1635年(一説によると1636年から1638年の間)、ベルニーニがフィレンツェのパルジュッロ美術館にいまも残るコスタンツァの胸像をつくったころには、ふたりの関係は決定的なものとなっていた。
胸像のコスタンツァは乱れ髪を軽くまとめ、かすかに眉をひそめ眼光鋭く、おちょぼ口ではれぼったい唇を、これからほほえもうとするその直前の瞬間といった感じで薄くあけている。寝巻きのような薄もののシャツの胸元のボタンは外されており、胸の盛り上がりが見え、あごの下にも十分に肉のついたその顔は、彼女の肉体がかなり豊満であったことを想像させる。貴族の女性のつくり上げられた美しさというより、太陽の下で汗をかき、服装の乱れも気にせずに働く農婦か洗濯女の色香(事実、彼女の父親は馬丁であった)。ベルニーニはこの胸像をみずからのために製作し自宅に飾っていたのだ。
恐れるものをもたない独裁芸術家と、彼のアシスタントの「妻」との関係は、貞操観念と男性にたいする劣勢、従順のみが女性に求められていた時代ではあったが、結局のところ夫のふがいなさの反映でもあり、ローマの南国的な開放感も手伝って、それを表立って批判する向きはあまりなかったようだ。ベルニーニが1628年からたずさわっていた法王の墓碑の製作にあたり、その一部をなす「慈愛」の像、乳房を赤子に含ませている女性像のモデルにコスタンツァを選んだときも、法王はあえて反対はしなかった。自分のお気に入りの芸術家の愛人(しかも人妻)の半裸の姿がみずからの墓に後世も残ることに同意したのである。そのころに製作されたと思われる一枚の油絵がベルニーニの家にあった。画面にはふたりの肖像が描かれている。鏡に映ったコスタンツァを見つめるベルニーニの自画像であった。
ともあれふたりの蜜月は1638年までつづき、三文芝居的終局を迎える。コスタンツァがベルニーニの十三歳年下の弟ルイージとも関係をもっていたことが発覚したのだ。ふたりにかんするあらぬうわさを耳にしたベルニーニはある晩、翌日は郊外に出かけると嘘をつき、翌朝大聖堂の裏にある自分の工房に向かった。工房とコスタンツァの家とは目と鼻の先である。そしてそこで、着衣の乱れたコスタンツァに見送られ、彼女の家から出てくる弟の姿を目撃したのだ。
その後のベルニーニの行動は、感情的というにはあまりに凶暴なものであった。弟のあとをつけたベルニーニは、サン・ピエトロ大聖堂で鉄の棒片手に弟に追いつくと、肋骨を二本折るほどの勢いで殴りつけた。もしも通りがかりの人間がベルニーニを押さえなければ、きっと実の弟をたたき殺していたことだろう。しかしそれだけではない。家に戻ったベルニーニは、使用人にギリシャワインの大ビン二本と剃刀を用意させるとこう言ったのだ。「わたしからの贈り物だといってコスタンツァのもとへこのワインを持っていき、チャンスをみはからって彼女の顔を切り刻め」主人の命令にとりあえず使用人は従うが、彼女には運のよかったことに、この使用人には女の顔を切り刻む勇気がなかった。結果、傷害未遂のためこの使用人は追放となり、ベルニーニには罰金がかせられた。しかし「芸術の才すばらしく、まれなる人材で、ローマに栄光の光をさずける」という理由で、法王はベルニーニに無罪放免を言い渡した。
しかし、まだ終わりではなかった。無罪放免を言い渡されたベルニーニは、再度弟の命をねらったのだ。むき身の剣を持って家に入ったベルニーニは、泣いてとりすがる母に見向きもせずに弟を追いまわし、弟が表に飛び出すと、そのうしろを剣を振りかざしながらサンタ・マリア・マッジョーレ(Santa Maria Maggiore)教会まで追いかけ、ベルニーニの剣幕と権威にしりごみする聖職者たちをしりめに、悪言雑言をはきちらしながら教会内で弟を殺そうとしたのだ。ルイージはほとほと運の強い男とみえて、このときにも命は助かっている。哀れなのは、兄弟で殺しあう息子たちを見てしまった母親であろう。「まるで自分がこの世の支配者であるかのようにふるまう」この偉大だが尊大な息子を、なんとかしてやってくれ、と法王に直々の嘆願書を送ったのだった。
法王みずからがベルニーニを「更生」させるためにのりだし、ベルニーニがその説得に屈したのは1639年5月のことである。法王推薦の司教区弁護士の娘カテリーナ・テーツィオと結婚式をあげたのだ。ベルニーニ四十歳、カテリーナ二十歳。この親子ほども年のちがう妻との間に、ベルニーニはじつに十一人の子どもをもうけることになる。結婚の翌年、ベルニーニが昼に夜に愛でていたであろうコスタンツァの胸像が、フィレンツェのメディチ家にひきとられた。新妻がその存在をよかれとしなかったのは想像のつくところである。ベルニーニは快諾したのだろうか。おそらく妻の手前そうであったろう。いや、彼がみずからそうしたのかもしれない。実の弟との裏切りという形で彼との関係を踏みにじった女だ。しかももともと人妻ではないか。三人の男を手玉にとった悪女の顔など見たくないのが当然だ。
しかし、実のところ、彼の心中はいかばかりのものだったのか。
コスタンツァの胸像がベルニーニ家から消え、長男ピエトロが誕生した1640年、ウルバーノ法王の墓碑の一部である「慈愛」 の像の製作がはじまる。コスタンツァをモデルにしたあの半裸の女性像だ。サン・ピエトロ大聖堂の天蓋の後方、聖堂のもっとも奥まったところに、精霊のシンポルである鳩が陽光を背に光っている。そのすぐ右手にあるのが法王ウルバーノ八世の墓碑である。礼拝用の木製の長椅子がつねに並べられているため、残念ながら近づくことばできないが、双眼鏡でならなんとか見えるかもしれない。最上段で祝福のポーズをとる法王の両脇に女性がひとりずつ立っている。奥が「慈愛」だ。製作された当時はむきだしになっていた左の乳房は、後世になって検閲にひっかかり、しつくいの布で隠されてしまった。その布越しの乳房に男の赤子が頬と唇をよせている。いっぽう彼女の右側には、子どもが泣きべそをかきながら彼女の衣服にしがみついており、彼女はその子どものほうに頭をかたむけ、それを優しく見下ろしている。ふくふくとした手の甲や丸みを帯びたあごのラインから、どちらかというと肉づきのよい女性像であることがわかる。低いところでゆるくまとめられた髪。そしてちょっとすねたように突き出された唇の厚いおちょぼ口。
コスタンツァだ。
モデルを変えることはいくらでもできたろうに、いちどはその顔を剃刀で切り刻もうとまでした女の顔と身体を、ベルニーニは慈愛像に彫りこんだのである。それだけではない。四年にわたるこの像の製作期間中、長男ピエトロは働く父の周りにちょこちょことまとわりついていた。また完成の年までに、ベルニーニにはさらにふたりの子どもが生まれている。つまり慈愛を象徴するコスタンツァが抱いている子どもは、ベルニーニの子どもたちがモデルである可能性が高いのだ。ベルニーニはこの像のなかに、コスタンツァが自分の子どもを産み、それを法王が祝福するという実現できなかった彼の夢を彫り込んだのか。それともあの伝説のように、コスタンツァはベルニーニの子どもを身ごもっていたのだろうか。彼がよく知っていたコスタンツァの像はもう彼の家にはない。同じ顔の、しかし魔性をすっかりとりのぞかれた美しいコスタンツァの姿だけが、大聖堂に残った。
妻に遅れること七年、ベルニーニが八十二歳に十日足らずで息をひきとったとき、主のいなくなった彼の部屋から半分に引き裂かれたあの油絵が見つかった。残っていたのはベルニーニの自画像の部分のみである。鏡のなかのコスタンツァがいつ、どこへいったのかはだれも知らない。
あの天蓋の台座の謎は、伝説と理論の間できっといつまでもゆれつづけるのだろう。ベルニーニが愛と憎しみの間でゆれていたように。
ローマ・ミステリーガイド 市口桂子
 参考文献
参考文献