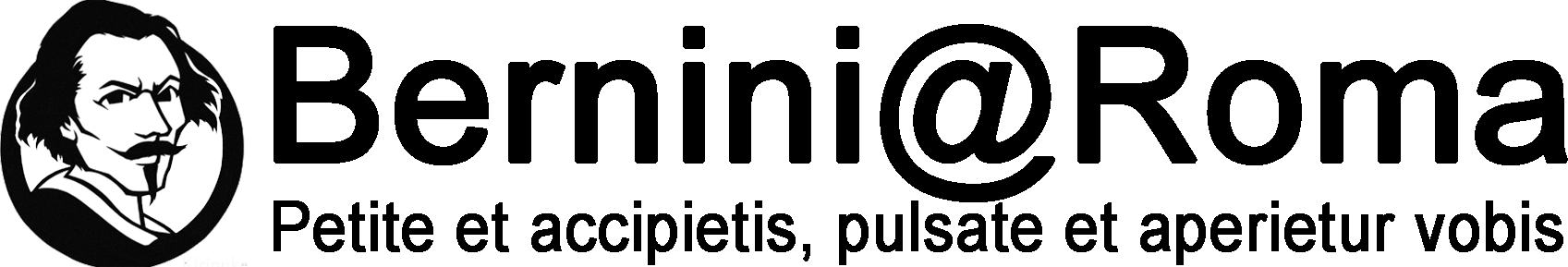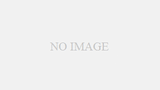《プロセルピナの略奪》に続いて、1622年8月にベルニーニは《アポロとダフネ》の制作を姶め、翌年の2月にはまだ制作を続けていたことが知られている。だが同じ年の夏には、もう一つの作品《ダヴィデ》に着手し、翌年の春までにこれを完成する。その後再び《アポロとダフネ》にかかるが、完全に什事を終えたのはようやく1625年になってからであった。しかし《ダヴィデ》を始めた時には、この作品はすでにかなり出来上がっていたと想像される。そこで《アポロとダフネ》を先に考察しようと思う。
この作品もオヴィディウスの『転身物語』に基づいている。恋心を生む黄金の矢を射られたアポロが、恋を嫌う鉛の矢を受けたダフネを追い求めるという、有名な月桂樹の転身物語の一節である。それとおなじように、神は希望にかられて、乙女は恐怖におびえて、ともに疾駆する。しかし、恋の翼にはこぱれる追手の方が脚が早く、相手にやすむひまもあたえず、すぐ背後に追いすがり、その息は乙女の頸になびく髪にふりかかる。乙女は、もう力の限界にきて、まっ蒼になり、ながいあいだひたすら走りつづけた緊張のために精根もつきはて、ペネウスの流れをみとめるなり、こうさけんだ。「お父さま、あなたの流れに神通力があるものなら、どうかお助けくたさい!みんなのこころをまどわしすぎるこの美しい姿を変えて、わたしをほろぽしてください」
ダフネがこの切なる祈りを言いおわるやいなや、はげしい硬直が手足をおそった。と、見る見るうちに、やわらかい胸は、うすい樹皮につつまれ、髪の毛は、木の葉にかわり、腕は、小枝となり、ついいままであれほど早く走っていた足は、強靱な根となって地面に固着し、顔は、梢におおわれた。
(田中・前田訳、第1巻537-550)
ベルニーニはこのオヴィディウスの詩句をものの見事に視覚化した。バルディヌッチは「それは全く想像を絶する作品であり、美術を熟知した者の眼にも、また全くの素人の眼にも、常に芸術の奇跡と映ったし、今後も映るであろうような作品である」と述べ、この作品が完成するやいなや、「奇跡が起ったかのようにローマ中の人がそれを見に行った」、この作品によってベルニーニは「神童」という名声を得た、と伝えている。実際この《アポロとダフネ》は、ベルニーニの彫刻作品の中でもサンタ・マリア・デルラ・ヴィットーリアの《聖女テレサの法悦》と並んで特に有名で、新古典主義の風潮の中で彼の評価が地に落ちた時代にも、なお人々の称讃を集め続けたのである。
この作品でベルニーニは、《プロセルピナの略奪》で試みた新しい可能性を一気に極限にまで押し進めたといえる。物語のクライマックスの瞬間を捉え、あたかもスナップショットのようにそれを造形化し、観る者が絵画を見るように一目で全体を理解できるように工夫する。そのために大埋石をロウの如くに刻んで、躍動する動きを捉え、同時にレアリティと美しさを追求する。ベルニーニが意図したのはこのような彫刻であった。それは、いわぱ三次元の絵画であり、長く人々の心を捉えてきた「絵画は詩のごとく」という美学を彫刻で実践しようとしたのだといえよう。これを実現したベルニーニの「技巧」はほとんど彫刻の限界を越えているように見えるほどであり、ベルニーニ自身もこの先このような華麗な「技巧」を披露することはない。早熟の天才ベルニーニここに極まれり、というべきであろう。
後年パリでこの作品に言及したベルニーニは、ダフネの髪に「軽さ」が表現されている点を自慢しているが、「軽さ」は髪だけでなく、ダフネの体全体を支配している。そのために彼女は空中に浮遊しているような印象を与える。だがかつては、現在我々が見るよりも一層この印象が強かったと思われる。というのは、近代になって安定をよくするために岩の一部が補強されたからだ。原作の状態では、視覚的不安定さが動感と浮遊感をより一層喚起したことであろう。この独特の動感と浮遊感、そして物語の幻想的性格のために、この作品全体がレアリティを越えてファンタジーの世界に入ってしまったように感じる人は少なくあるまい。それはバレーを連想させ、アール・ヌーヴォーの遠い祖先のようにさえ見える。ことにダフネの右手の先の小枝が髪に連なる辺りを見上げると、大理石がまるで粘り気のある物質のように感じられ、アール・ヌーヴォーの作品を見ているような錯覚に襲われる。優れた美術家はしぱしぱいろいろな造形の可能性を先どりするのである。
こうした《アポロとダフネ》のファンタスティックな雰囲気は、レアリティの世界を越えてゆこうとする、ベルニーニの想像力の志向性をよく表わしている。こののち宗教作品を中心に制作するようになると、この志向性は超越的エクスタシー表現の探求という形で現われることになる。しかしながら、《アポロとダフネ》のこうした雰囲気は、この作品の他の重要な側面をおおい隠してしまいがちだ。
つまりファンタステイックな印象が強いために、この作品でもベルニーニは古代美術の研究から出発した、という事実を、ともすれぱ見過してしまうのである。先には触れなかったが、《プロセルピナの略奪》においても、プルトは1620年に発見されてシピオーネ・ボルゲーゼが所有していたトルソが、プロセルピナは《ニオベ》が、それぞれ範となっているといわれる。この《アポロとダフネ》では、アポロとヴァチカンの有名な《ベルヴェデーレのアポロ》との類似がとりわけ印象的である。実際、両者の頭部の比較はショッキングという他ない。《ベルヴェデーレのアポロ》の「アカデミックな」イメージとこの作品の詩的印象があまりにかけ離れているため、両者の歴然とした類似が意外の念を引き起こすからた。実際それは、今まで見てきた作品の一部だとは信しられないほどの類似である。この比較は、若いベルニーニがいかに古代美術から学んだか、そしてその成果をいかに自在に応用したかを示しているといえよう。この後、より「バロック的」作品を制作するようになっても、ベルニーニはしぱしぱ古代彫刻から出発している。たがその結果生まれた作品は、その事実を全く忘れさせてしまうのである。このような古代美術とベルニーニとの関係は、「古典主義」と「バロック」という言葉を、対概念を表わす用語として便宜的に用いる我々をしぱしぱ混乱に陥れる。古代美術との関係、広い意味での古典主義の間題は広くイタリア美術全般にわたる根本的間題の一つである。ベルニーニの芸術を考えてゆくためにも、われわれは幾度かこの間題に立ち帰らなけれぱならないであろう。
ベルニーニの次のパトロンになるマッファオ・バルベリーニ(ウルバヌス8世)が捧げた詩は、パリでも話題になるほどであった。今日も台座を飾るその詩は次のようなものである。
つかの間の美形を追い求める恋人は
苦い果実をむしり、手のひらを葉で充たす
少々危なっかしいところのある驚嘆すべき作品に、道徳的解釈を加えて免罪符を与えた、というところであろう。
アポロとダフネ
 参考文献
参考文献