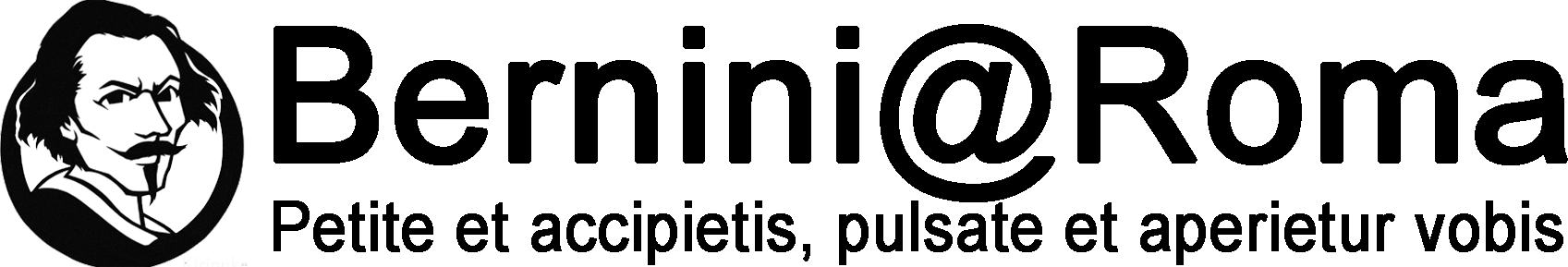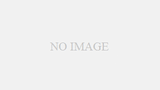教皇ウルバヌス8世の命を受け、1632年に制作する。
シピオーネ・ボルゲーゼは1633年10月8日に世を去るが、その前年にベルニーニは教皇の命を受けて彼の肖像を制作した。おそらく、教皇は教皇選挙の折に便宜を計ってくれた枢機卿への好意から、肖像の制作を命じたのであろう。ベルニーニがこれを喜んで引き受けたことは想像にかたくない。むしろ彼自身がこの計画を提案して、教皇の許可を求めたのであったかもしれない。そう思わせるほど、このシピオーネ・ボルゲーゼの肖像は生き生きしており、ベルニーニの親愛の情があふれている。シピオーネ・ボルゲーゼは座の中心にあって、何かゆっくりとした口調で話しているといった風だ。目も鼻も口も、それぞれが個性的で、それぞれが生きている。また衣装も光を巧みにもてあそび、全体の印象を暖かで、しかも格調のあるものにしている。シピオーネ・ボルゲーゼはこの時54,55歳だったが、肖像はそれよりも幾分若々しく、多少美化されていろように見える。肖像に若干の美化が必要なことは、ベルニーニ自身も認めている。彼は後にパリで「肖像の秘訣は美点をできるだけ利用して、全体に偉大さの印象を与えることである」と述べている。また、ルイ14世のくちびるの部分を仕上げながら、「肖像で成功するには、行為をとらえて、それをよく表現するよう努めなけれぱならない。くちびるの表現には、人が話を始める瞬間か、言葉を発した瞬間を選ぶのが最もよい」とも語っている。美術史家が「会話する肖像」と呼ぶ肖像のタイプは、こうした発想から生まれたのである。
肖像を作ろうとする場合に、その人物の特徴を捉えるベルニーニの方法は独特であった。ドメニコは次のように伝えている。「彼はモデルがじっとしているのではなく、いつものように自然に動いたり、話したりしているのを望んだ。そうすることによって、そのモデルの美しさを総合的に見ることができるからだ、と彼は言っていた。人がじっとしている時には、動いている時ほどその人らしくは見えない。動きの中には、他の人ではないその人の性格すべてがあり、それが肖像にその人らしさを与えるのだと主張して、彼はモデルをあるがままに表現した、このような考え方を、ベルニーニは実際の肖像制作に生かしていたのである。たとえばパリでルイ14世の肖像を手がけた時にも、王がテニスをしたり、会議や謁見に臨んだりしている姿を観察してデッサンしているし、また王がミサに出席しているところを見ようと、わざわざ出掛けたりしている。ベルニーニがこうしたデッサンを描いたのは、モデルをよく観察してその特徴を捉え、そのイメージを脳裏に焼きつけるためであった。
「それだから、私はデッサンを(作品の制作には)ほとんど利用しなかった。自分の作品をコピーするのではなく、オリジナルな作品を創造したかったからである。それらのデッサンは、ただ私を王のイメージで充たすために描かれたのだ」とベルニーニは説明している。この種のデッサンはもしも残っていたならぱ、ベルニーニの制作過程を知る上で貴重な資料になったにちがいないが、残念ながら一点の例外を除いて、まったく我々の手には伝えられていない。
その残された一点が、モーガン・ライブラリーにあるシピオーネ・ボルゲーゼの肖像である。 このすぱらしいデッサンは、モデルを観察する際のベルニーニの集中力と気魄をよく伝えている。ここに描かれているのは、往年の活力を失った、実際のままのシピオーネ・ボルゲーゼである。これと比べると大理石の胸像は、先に述べたように幾分美化されているように見える。しかし、それは単なる美化ではなく、ベルニーニが捉えたシピオーネ・ボルゲーゼらしさを純化した結果、実際の姿から少し離れることになったと解すべさであろう。このような、モデルからその人らしさを摘出するベルニーニの天才的な能力は、シピオーネ・ボルゲーゼのもう一つの肖像ともいうべきカリカチュアによく現われている。この軽妙なカリカチュアを一見すれば、誰しもがすぐにシピオーネ・ボルゲーゼその人と分かり、微笑を禁じえないことであろう。あたかも観者に話しかけるような、こうした「会話する肖像(リトラット・パルランテ)は、以上述べたように、肖像にその人らしさを与えるために発想されたものであった。が同時にそれは、観る者を作品の空間に誘い込むための、一種の技巧だと見ることもできる。つまり、この肖像彫刻の新機軸も、ベルニーニの他の彫刻作品と同じ発想に基づいているのだ。すなわちそれは、現実の空間と作品の空間との境を取リ除いて「劇的効果」を達成しようとする発想の、今一つの現われなのである。
最後に面白いエピソードを書き添えて、シピオーネ・ボルゲーゼの肖像に間する話を終えることにしよう。肖像の制作が最終段階に入った時、額のところにひびがあるのが発覚した。そこでベルニーニはこの肖像が完成すると、すぐさま品質に間違いのない大理石を用意して、まったく同じ肖像を制作した。彼はこの第二の肖像を、バルディヌッチによれば19日間、ドメニコによれぱ昼夜3日で仕上げ、仕上がるとシピオーネ・ボルゲーゼをアトリエに招いた。枢機卿はその出来映えに満足したが、やはリ額のひひが気になる。しかし紳上たる枢機卿はそれを面に出さずにいると、ベルニーニは何くわぬ顔で会話を交わしてから、第二の完壁な肖像を披露し、シピオーネ・ボルゲーゼを大いに喜ぱせたというのてある。この二つの肖像は、今日もボルゲーゼ美術館に対にして飾られている。第二の肖像はやや生気に欠けるところかあり、第一作には及ぱない。たがベルニーニの手に成ることは疑うまでもない。つまりエピソードは紛れもない事実なのである。このようにベルニーニは、実際の生活でも今日の我々の目から見れぱ少々芝居がかった趣向で人々を喜ばせた。このエピソードは、そうした事柄に対する彼の情熱を実感させてくれる。なお、一つのアイディアを得るとその実現に異常なまでの集中力を発揮したべルニーニが、この第二の肖像をごく短期間で仕上げたことは容易に想像のつくところである。