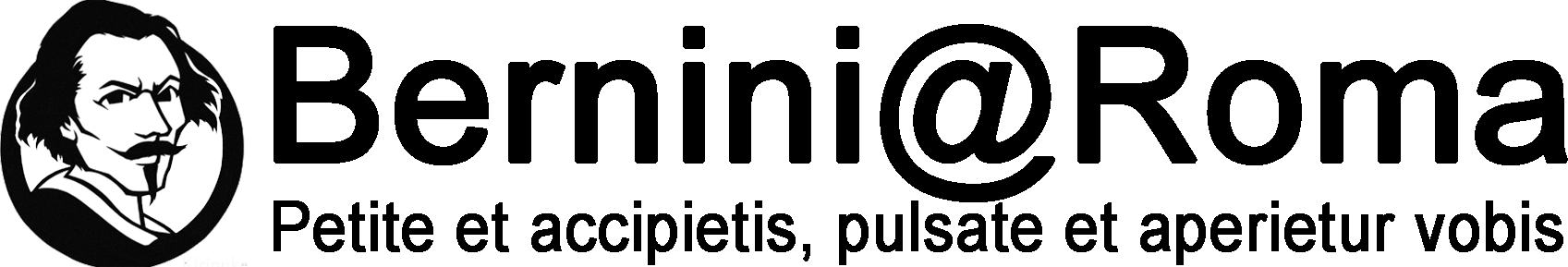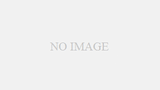「ダヴィデ」 Davide
シピオーネ・ボルゲーゼの注文。1623年8月から24年にかけて一気に仕上げた。
《アポロとダフネ》の制作を一時中断して、ベルニーニが1623年の8月から、《ダヴィデ》を一気に仕上げたことはすでに述べた。「この作品(《ダヴィデ》)において、彼は彼白身をもはるかに凌駕し、わずか7カ月の間にこれを完成した。というのは、このように若いうちから、彼が後によく語ったように、彼は大理石をむさぼり、決して無駄なのみを使わなかったからである」とバルディヌッチは記している。このバルディヌッチの言葉は少しも誇張とは響くまい。なぜなら、ベルニーニの仕事の量、その早さ、そして作品に見られる集中感は、彼が強靱な意志と体力の持主であり、そしていかに並外れた集中力に恵まれていたかを痛感させるからだ。バルデイヌッチが他の箇所で伝えるところによれぱ、建築の仕事がない限り、彼は7時間も統けて大理石彫刻にとり組んだ。これには若い助手もついてゆけず、ある者が仕事を止めさせようとしたことがあった。するとベルニーニは、「このままにしておいてくれ。私は虜になっているのだから」と答えたという。彼はいつも、あたかも恍惚の状態にあるかのように仕事をした。その集中力はあまりに強かったので、足場の上では助手が付き添って、落ちないように見張っていなけれぱならなかった。また、しぱしぱ枢機卿や諸君主が彼の仕事場を見にやってきたが、その仕事ぶりに息をのみ、しぱらく見物してから、挨拶もせずに立ち去ることが多かったという。それにしても、この規模の作品の制作に7カ月というのは驚くべき早さである。しかし、それを事実だと信じさせる、若々しいヴァイタリティがこの作品には感じられる。
いうまでもなく、ダヴィデは旧約伝の英雄である。彼がペリシテ人を破るくだりは『サムエル記』(第1、17)にある。
ダヴィデ像は多くの彫刻家によって繰り返し作られてきたが、なかでも思い浮かぶのは、何といってもドナテルロとミケランジェロの《ダヴィデ》である。このうちドナテルロの《ダヴィデ》は、剣を奪ってゴリアテの首をはねた勝利のダヴィデを、美少年として表わしたものである。これに対してミケランジェロは、ドナテルロに見るようなダヴィデの一般的タイプを全く顧みず、戦いに臨む直前のダヴィデを、精神的緊張を全身にみなぎらせた青年として作り上げた。どちらもすぱらしい作品だが、ミケランジェロの《ダヴィデ》は横想のユニークさにおいて際立っている。だがベルニーニの《ダヴィデ》も、これに劣らず独創的だ。彼は単なるダヴィデの像ではなく、ダヴィデとゴリアテの物語そのものを造形化しようとしたのだ。この物語のクライマックスが、ダヴィデが石を放ってゴリアテを倒す場面にあることは、誰の目にも明らかである。したがって、ダヴィデが渾身の力を込めて石を投げる瞬間を、ベルニーニは捉えたのである。
このベルニーニの《ダヴィデ》とミケランジェロのそれとの比較は、いろいろな示唆を与えてくれる。まず気づくのは、ミケランジェロの構想が非常に観念的なのに比して、ベルニーニは平易な図解を目指している。トルナイによれぱ、ミケランジェロは共和国のために戦う市民の二つの美徳、すなわち「剛毅」と「忿怒」の化身として、ヘラクレスになぞらえて《ダヴィデ》を制作した。つまり彼の時代には、この作品は政治的意義を有していたのである。だが今日、何も知らずにこの彫刻を見て、それがダヴィデの像だと分かる人が幾人いるたろうか。この作品があまりに有名なために、我々はそれがダヴィデであることに疑間を抱かないだけではなかろうか。というのは、この作品はミケランジェロがダヴィデとはこのようなものだと考えたダヴィデ以外の何物でもないからだ。ミケランジェロは物語の中核には全く触れず、物語をうかがわせる事物を石の入った袋だけに限定し、それさえ正面からは見えなくしているのである。一方ベルニーニは、ダヴィデのドラマを万人に分かるように視覚化しようとした。彼の主眼は物語の決定的瞬間におけるダヴィデを表わすことにあったが、聖書の記事に従ってダヴィデを説明することも忘れてはいない。ダヴィデは石を入れた「羊飼が使う袋、投石袋」を肩にかけ、足もとには、サウルが着せてくれたが彼が嫌って脱ぎ捨てた鎧兜が置かれている。さらにその下からは、鷲をかたどった竪琴が顔をのぞかせているのである(鷲はシピォーネ・ボルゲーゼの紋章である。このことからドノーフリオは、ダヴィデはシピオーネの政敵ルドヴィーコ・ルドヴィーシを倒そうとしているのだ、と解釈した)。こうした事実は、ルネッサンスとバロックにおける美術と美術家のあり方の違いを考えさせる。ルネッサンスにおいては、新プラトン主義の風潮の中で、美術はそれ自身存在意義をもつと考えられ、ある程度自己完結的に存在しえた。一方バロック期になると、美術は何らかの社会的役割を果すよう要求されるようになる。つまり美術はあらゆる種類の宣伝に用いられ、そのためレトリックを駆使して、できるだけ多くの人々の心を動かすよう工夫されるようになるのである。それと同時に、新プラトン主義的な天才の概念やその神秘に対する称讃は失われて、美術家は再び地上に帰る。この二つの時代の美術と美術家のあり方は、ミケランジェロとベル二ー二に象徴的な姿で現われているといえよう。こうした時代の違いは、同時に造形にも現われている。《ダヴィデ》においてミケランジェロは不朽の造形、モニュメンタルな肉体を迫求したが、ベルニーニはあくまで瞬間の動きと緊張を捉えようとしている。崖から落してもびくともしない彫刻が望ましい、という有名な言葉からも分かるように、ミケランジェロは堅牢な人物像を至上とした。また彼が「削りとる」彫刻を重んじて、「付け加える」塑像をひどく軽蔑したことはよく知られている。これに対してベルニーニは、《ダヴィデ》において、《プロセルピナの略奪》や《アポロとダフネ》ほどではないにしても、ミケランジェロがさげすんたブロンズ彫刻の表現力を大理石で達成しようとしたように思われる。このように、二人の巨匠は大理石彫刻を天職と考えた点では共通しているが、その大理石から創り出そうとした造形は全く異なるものだったのである。しかしその造形を生み出すに当って、二人とも古代彫刻の研究から出発していることも忘れるわけにはゆかない。ミケランジェロの《ダヴィデ》が際立って「古典的」であることはしばしば指摘される通りだが、一方ベルニーニの方も、ルーヴル美術館にある《ボルゲーゼ・ガリタトール》などから霊感をえていると考えられる。どちらの場合も、その造形の基本は古代彫刻の研究にあるのである。ここにも、先に触れたイタリア美術史の根本間題が姿を現わしている。
ベルニーニの《ダヴィデ》について、どうしても触れておかなけれぱならないことが二つ残っている。一つは、この作品も他のボルゲーゼの彫刻と同様に壁につけて置かれていた、つまり基本的視点がはっきり設定されていたということてある。そしてもう一つは、その基本的視点に立つ観者を、彫刻の生み出す空間に誘い込もうとベルニーニが意図していることである。ミケランジェロの《ダヴィデ》にも、ダヴィデが鋭く見つめる彼方にゴリアテがいる、と感じさせる一種の心理的働きかけがあるといえる。たが彫刻自体の強い完結性のために、それはあまり重要には感じられない。これに対してベルニーニの《ダヴィデ》では、見る者に物語を感じさせる、より現実的な配慮がなされている。つまり、このダヴィデは明らかにゴリアテに向って石を投げようとしているのであり、それを見る我々は背後にその相手の存在を想定せざるをえないのた。こうして我々は知らず知らず物語の空間に引き込まれてゆくわけであるが、このように見る者をいわぱ物語の証人として、彫刻の生み出す空間に誘い込もうとする意図は、これまで述べた作品にもみられた。けれどもこの《ダヴィデ》では、それが一層具体的な形で構想されているのである。こうした見る者と作品、現実の空間とフイクションの空間との間にある心理的障壁を取り除こうとする発想は、ベルニーニの造形世界を特徴づける重要な要素である。ベルニーニの、そしてバロックの美術を鑑賞する者は、しばしば現実の空間と美術の空間の境を見失う。それはミケランジェロの、そしてルネッサンスの世界では決して体験でさない、バロックの魔術の世界である。
最後に伝記作者が伝える興味深いエピソードをそえて、《ダヴィデ》のもとを去ることにしよう。ベルニーニはダヴィデの顔を彼自身をモデルに制作していたが、ある日アトリエを訪れたマッフェオ・バルベリー二(後のウルバヌス8世)が、ベルニーニのために鏡をもってやったという逸話である。このエピソードは、ベルニーニ自身もパリでシャントルーに語っている。この《ダヴィデ》の顔が一種の自刻像であることは、同じ時期の《自画像》からほぽ確認することができる。
ダヴィデの表情に、呪われた魂を参考にしている。